今回は、天体望遠鏡購入にあたって「初めて望遠鏡を買おう」と思っておられる方に選ぶためのポイントについて書きたいと思います
天体望遠鏡購入時に考えるべきポイント7つ
- 口径:あなたが観察したい天体を見るのに最低どのくらいの口径が必要かを考える
- 望遠鏡方式:屈折式望遠鏡か反射式望遠鏡か(詳細は以前-1で説明)
- 架台方式:あなたが観たい天体に対応するのに経緯台式で可能か、赤道儀式が必要かを考える
- 観察方法、環境:観察する時自宅庭や公園、その他の場所へ移動させることがあるか
- 架台、三脚
- 予算、費用面
- オプション(番外)
口径
天体望遠鏡での口径は非常に重要なポイントです
口径が大きいほど「集光力」があり「分解能」があります
- 「集光力」は何光年も遠くの弱い光をどれだけ沢山望遠鏡内に集めれるかです
- 「分解能」とは口径が大きくなるほど高く、非常に近い二つの天体をどれだけ細かく見分けられるかと言うことで惑星の縞模様や二重星の分離などです(光学系の品質が良いほど高くなる)
分解能(秒角)=116÷口径(mm)となります
光の波長などが関係しますが、116は定数として計算して、分解能(秒角)が分かります
小さいほど分解能が高く細かく観察し易いと考えられます
月は明るく50mmや60mmの口径でも観れますが、これが惑星を観たいとなると最低80mmの口径は欲しいです
加えて焦点距離も長い方が有利です
土星や木星を60mmでも見えないことはないでしょうが、小口径だとハッキリと細かな部分(木星の縞模様や土星の環の隙間など)までは見え辛くなると言う事です
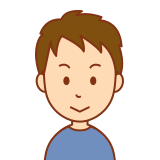
それなら、倍率を上げればいいのでは?
これは初めて望遠鏡を探す人の勘違い「あるある」です
倍率を上げれば大きく良く見えると思いがちですが、上げすぎると像が暗くなり、ぼやけて見え難くなります
「限界倍率」と言うものがあり
「これ以上倍率を上げても像が暗くてぼやけるだけ」という上限です
実用的に使える限界倍率で
だいたい倍率を上げることで分解能の限界を「目で認識できるサイズ」まで拡大できるのが
口径(mm単位)の2倍とされ、これを超えて倍率を上げても、それ以上細かい物は見え辛くなります
- 口径60mmで約120倍
- 口径80mmで約160倍
- 口径100mmで約200倍
このように見えやすいように倍率を上げるとしても口径は重要な要素で、大口径ほど有利と言えば有利です
また同口径であっても光学系の違いで変わってはきます
ざっくりとした考え方として、天体を観察するには大口径ほど、分解能が高くて集光力があり観測に有利であると思ってください
望遠鏡方式
屈折式望遠鏡か反射式望遠鏡かハイブリットか
詳細については「天体望遠鏡を買いたい-1(方式)」に書いておりますので下記をクリックしご参照ください
これも重要な選択のひとつで、
屈折式望遠鏡はシンプルな構造で反射式ほどメンテナンスを必要としないですし入門者、初心者には扱いやすいです
ただ大口径を求めると高価なものとなります
反射式望遠鏡は大口径でも意外と低価格で手に入れることができますが、少しメンテナンスが必要な部分があります
逆にこれからメンテナンスも含めて天体観測を楽しむという考えも良いと思います
この両方を組み合わせたハイブリットのカタディオプトリック式と言う機種も最近は良く見かけます
レンズと鏡を併用
大口径で長焦点を得やすく、光軸修正もニュートン式反射より頻度も少なくて済むと思います
架台方式
大きく分けると経緯台式と赤道儀式があります
経緯台:カメラの三脚と同じような感じで、上下用ハンドルと左右用ハンドルが付いており天体、星の動きに合わせて両ハンドルを動かすことで斜めに天体(星)を追いかけるイメージです
ハンドルはフレキシブル微動ハンドルが使い勝手が良いです
赤道儀:極軸合わせが必要で、北半球でしたら赤緯軸を北極星に合わせればほぼいけますが(精密には天の北極へ)、観察前にその作業が必要です
合わせてしまえば、赤経軸用ハンドルで星を追尾できるので便利です
さらに自動で追随できる装置をオプションで取り付けることも可能です
詳細については「天体望遠鏡を買いたい-2(架台)」、に書いておりますので下記をクリックしてご参照ください
観測(観察)方法(環境)
天体観測の為の望遠鏡が、どこかある観測場所に設置して移動することがほぼないのであれば、大口径で重量があっても問題はありません
また毎回同じ場所で観測が出来る環境であれば、赤道儀の極軸合わせもそれほど苦にはならないと思います(小さなお子さまには困難なので、大人の方の協力が必要でしょう)
逆に常に移動が前提で、また観測のためのキャンプなどで車で運ぶのが常と言う人にとっては軽くてコンパクト、移動させるのが楽な機材を選択するのも手でしょう
ここでコンパクトなので屈折式小口径と考えないで、大口径ハイブリット式で移動可能なシュミットカセグレン式も検討されると良いと思います
基本、天体観測の環境は光害の無い澄んだ夜空がより良いと言う事を前提に、自分の観測環境がどうなのかも理解しておくと良いでしょう
あなたが観測される場所が光害のある「都会」で、観測したい対象が「星雲」となると光害の無い星の良く見える暗い場所への移動が必要と考えられた方が良いです
明るい惑星なら都会でも楽しむことは可能ですが、星雲、星団となると暗い環境が必要であることを考えていないと、光害の多い環境で大型の望遠鏡を購入してから移動手段もなければ、観たい対象物によっては、活かせずに悲しい結果となってしまうので、その辺りにも気を付けて望遠鏡の選択肢としてご検討ください
三脚
架台(マウント)としての赤道儀や経緯台その上の天体望遠鏡の鏡筒
この二つでかなりの重量になります
これを支える三脚
これは頑丈な物でなければなりません
下の土台がしっかりしていないと、遠くの天体(星)を視野内に捉えていても
ふらふらゆれると観察出来ないです
安物の望遠鏡と言っては何ですが、いかにも風でゆれそうな三脚の望遠鏡では良い観測は出来ないと思ってください
天体写真でなくてもカメラをされている人なら良くご存じだと思います
どれほど三脚が重要かを…
スマホで撮影していて手振れを経験されたことがあると思います
人が手にもって撮影すると固定が十分でなくブレる(最近は手振れ補正されている)
これが天体望遠鏡だと対象物が望遠鏡内に静止したように収まらず、ゆれて良く見えなくなります
天体望遠鏡にカメラを設置して天体写真を撮りたくてもブレて良い写真が撮れないことになる
三脚にはアルミやカーボン、円柱型ピラーなど上部の架台や望遠鏡が大きくなるほどそれを支える頑丈なものが多いです
鏡筒に比べて余りにも大きく頑丈なものとなると、かえって重くなるのでバランスを考えて下さい
天体望遠鏡を選ぶ上ではこの三脚、土台部分もしっかりとした物を選ぶ事が重要です
費用面
ある意味この費用面、予算と言うのが一番重要なのかも分かりません
ただ、観たい対象物に対してゆずれない部分を優先的に考え、予算配分する事が重要だと思います
例えば惑星を楽しみたいなら、高倍率でシャープでクリアに観たい
そうなるとある程度口径が大きい物でないと倍率を上げ辛くなる
倍率は、望遠鏡の焦点距離÷接眼鏡の焦点距離です
そして倍率は「1.口径」で書きましたが、
口径(mm)の2倍程が限界倍率で、1~2倍程度が適正倍率となります
- 口径100mm、焦点距離1000mm、接眼レンズ5mmを使用すると1000÷5=200倍で限界倍率ですが、適正倍率範囲内です
- 口径50mm、焦点距離600mm、接眼レンズ5mmを使用すると600m÷5=120倍で口径の約2倍とされる限界100倍を超えてきます
使用できない訳ではありませんが、暗くなりぼやけてクリアな像が観れなくなります
クリアと言う表現が難しいですが、細かな惑星の縞模様となると「分解能」が高い方が良いです
上記(1.口径)でも示しましたが、分解能は「秒角」が小さいほど優れている
- 口径100mmなら116÷100=1.16秒角
- 口径150mmなら116÷150=約0.77秒角
このように口径が大きいほうが分解能も集光力も得られやすく、また見やすいように倍率を上げる事も可能という事になります(口径で決まる分解能を超えて倍率をいくら上げても細かくは見れない)
つまり話を元に戻せば、惑星を観たいなら
屈折式ED/アポクロマート
口径100mm~120mm
焦点距離1000mm前後
f値10~15(焦点距離÷口径・カメラと同じで数値が小さい〔f4~6〕ほど明るく広角)f10~15惑星観測向き)
架台は「赤道儀」とした場合、
屈折式で大口径、長焦点、赤道儀となるとかなり高価で重量もある
口径と重量は良いとしても、この選択で予算内だと良いのですが、
予算以上だと再検討しなければなりません
- 口径を少し小さくするのか
- 赤道儀を経緯台に変更するのか
- 光学系アポクロマートレンズをアクロマートレンズにするのか
もし予算オーバーなら、対象物を見る為の機材を予算内に収める為に上記部分を再検討し
変更をしなければならなくなります
その時に「自分が譲れない部分(口径、架台、方式等)」を決めておく事です
その方が検討し易いですし、後悔がないです
もう一つ
方式の変更なら、反射式で大口径を得る方法もありますし、
カタディオプトリック式なら大口径と更に惑星観察に長焦点も得やすいです
シュミットカセグレン式なら量産されているものなどは、安価に手に入れれます
方式を変更すれば、望みの部分をある程度予算に合った機種として入手可能となる場合があります
屈折式よりはメンテが必要になると思いますが予算面を考える上で重要な要素です
オプション部品(番外)
天体望遠鏡そのものではありませんが、番外として購入した天体望遠鏡のオプション品や後からの部品追加購入に関しても重要な要素になる場合もあります
現在では、様々なネット販売もありますので、私の頃の様に部品購入に困ることはないと思いますが、それでも光学製品ですし、もし大型専門店や量販店で確認してから直ぐ購入可能だと保証面も含めてより安心だと思います
以上、番外も含め7つのポイントを参考に検討されれば、おそらく自分の思いの機材に少しは近づけると思います
良き機材との出会いを願っております








コメント
ともちゃん最高‼︎親切丁寧わかりやすい‼︎
解説見て思わず買っちゃいました‼︎
これからも楽しみにしてます❤️
コメントありがとうございます
いつも投稿をお読みいただき、ありがとうございます
何かのお役に立てれば嬉しいです
投稿を続けて行きたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします